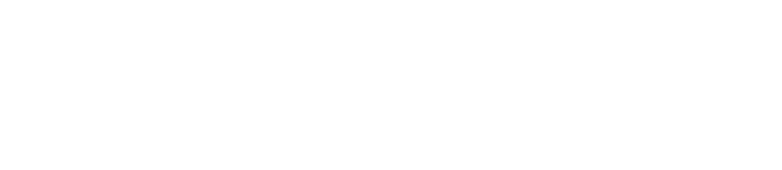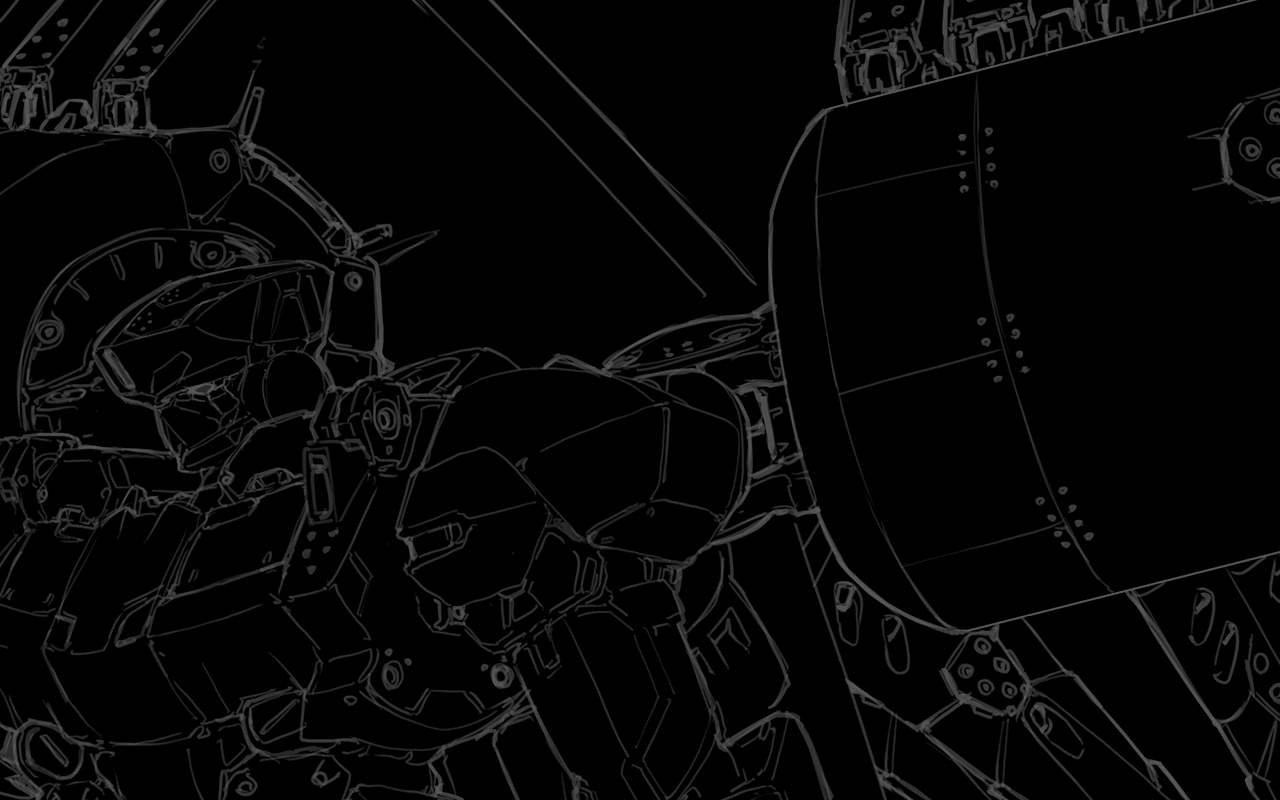INTRODUCTION
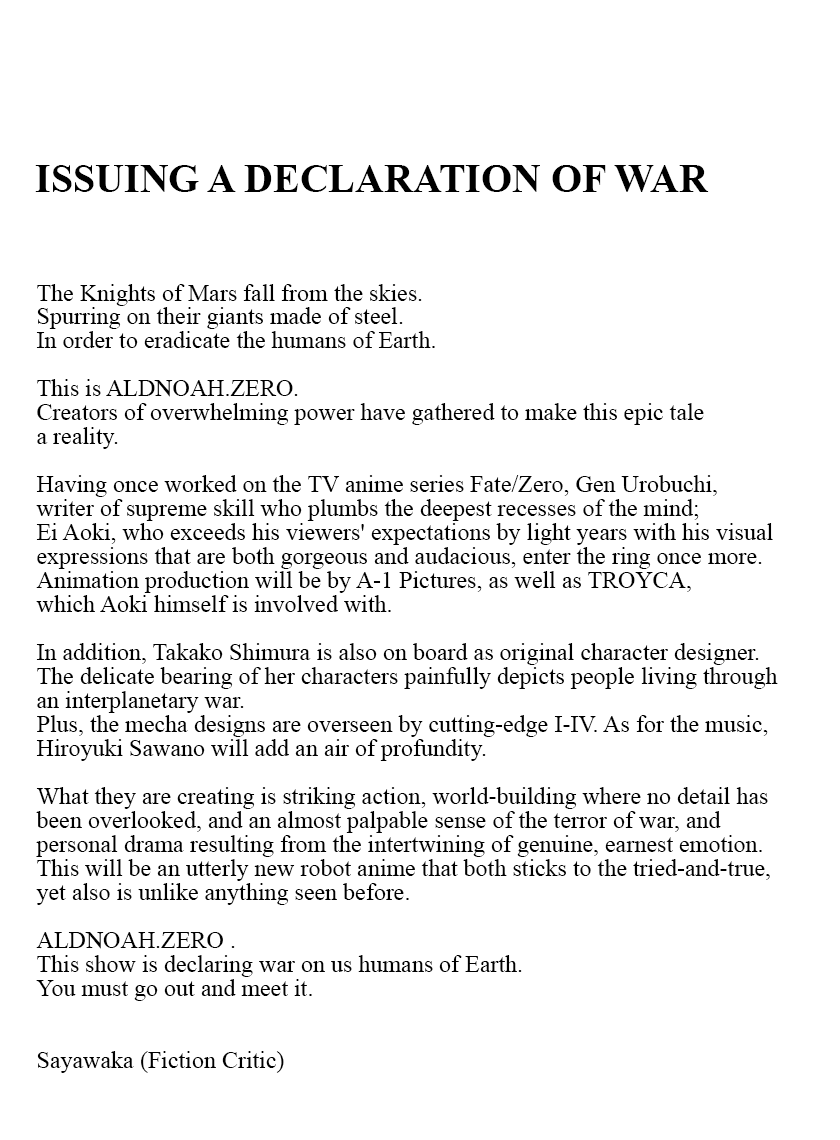


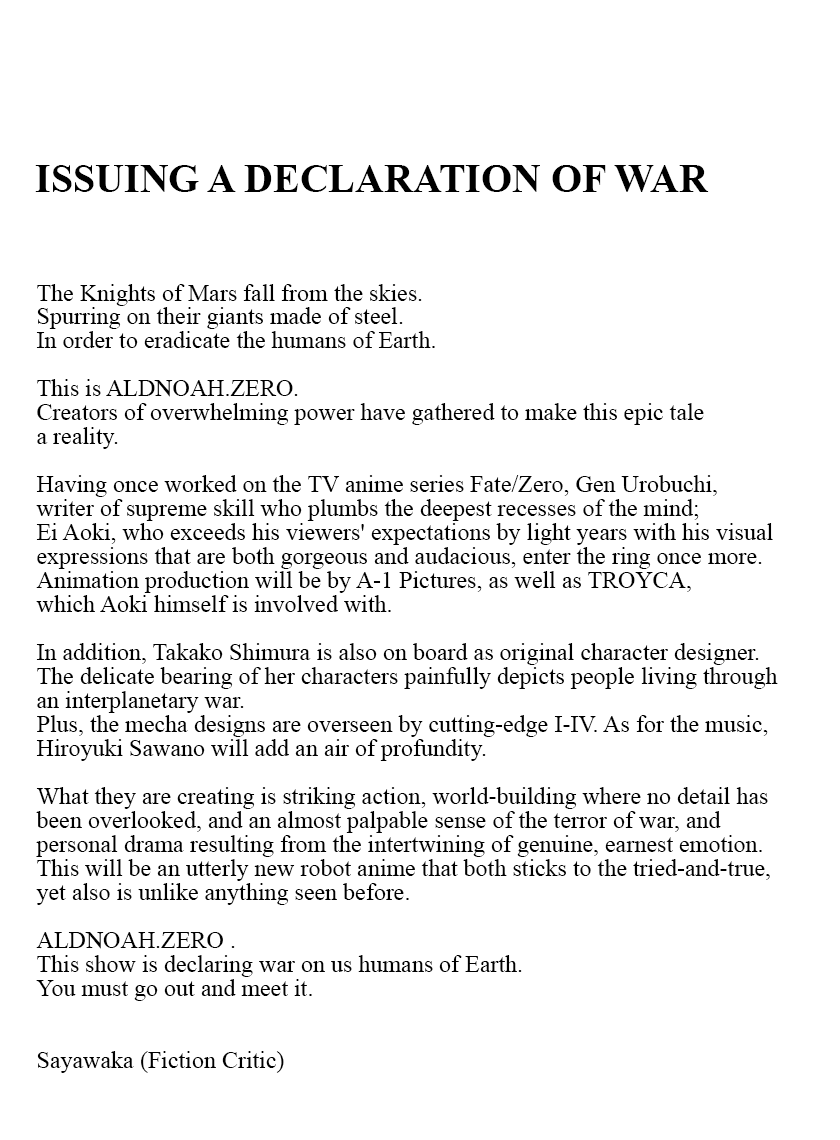
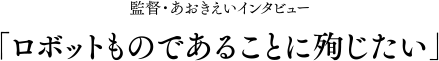
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
まだ『Fate/Zero』を作っていた頃、アニプレックスの岩上プロデューサーから「少年少女が主役のロボットものをやりませんか」と言っていただいたんです。ロボットものって、たとえば「スーパーロボット」と「リアルロボット」のようにジャンルの中で細かく方向性が分かれると思うんですけど、僕がその時に聞いた感じでは、リアルロボットと呼ばれるような方向性だと思いました。それで自分からもアイデアをいくつか提示しました。
―リアルロボットの方向性というと、具体的にはどういうものを想定していましたか?
そもそも少年少女がロボットに乗るというのは日本のロボットアニメの伝統ではあると思うんですよ。だけどリアルロボットの系譜が持ち込んだ新機軸って「戦争」なのかなと自分では考えています。昔のスーパーロボットもののロボットアニメは、悪い異星人や科学者、つまり絶対悪の存在がいて、それと戦うために少年少女がロボットに乗る、という話だったと思うんです。でもそこでロボットとはつまり兵器であり、戦いとは戦争なのだという要素を持ち込んだのがリアルロボットものですよね。だから『アルドノアゼロ』も、少年少女が戦争に巻き込まれて、兵器としてのロボットで戦うアクションものとして考えていきました。
―ということは「正義と悪」というような、わかりやすい対立のある物語ではないということですね。
そうですね。火星と地球という2つの陣営に分かれて戦うストーリーになっているんですが、火星側もいわゆる
異星人ではなく、もともと地球人なんだけれども火星に移民していった人たちという設定になっています。
―どちらが正しいというわけでもない、複雑な人間ドラマがある作品というわけですね。
地球側の陣営としても、群像劇になると思っています。当然、主人公にストーリーを引っ張っていってもらわないといけないんですけど、同時にみんながそれぞれ戦うことで戦争という状況そのものをきちんと描きたいな、と。リアルにしすぎるとまた方向性が変わってしまうので、難しいところなんですが。軍服を着た人ばかりが出てきて戦う、あまりにもリアルなものにはしたくはなかったんですよね。そのあたりのバランスについては、虚淵さんや岩上さんとずいぶん話し合いました。やはり虚淵さんは戦争を格好よく、男らしく描いてくださるんですよね。だから僕はそこに少年少女の要素を足していくという役割を担当しながら作っていきました。
―リアルさを強調しない方向性になった理由はなぜですか?
やはり、主人公たちと同年代の男の子や女の子も含めて、楽しんで見られるものにしたいと思いましたので。政治や軍事的な要素もバックボーンとしてはあるけれども、あまりにもそういう部分ばかりになると、主人公たちの年代から見た世界とは少しかけ離れてしまうと思うんですよね。あくまでも主人公たちは、大人たちと同じ目線で戦争をするというよりは、自分たちに降りかかった火の粉をどう払うかという戦いをすることになるのではないかと考えています。10代の男の子や女の子が見る「戦い」という感じを、うまく出せればいいなと。
―タイトルにある「アルドノア」とは一体何なのでしょうか?
そもそも地球人類が火星に移民したことには理由があるんです。火星で先史文明が発見されて、しかもそこには超科学的なエネルギー源がある。それをいま「アルドノア」と呼称しているということなんです。
―舞台として火星が選ばれたことには、理由がありますか?
全く未知の星にするというアイデアもあったんですが、最終的には地球との距離感も一番よい火星になりました。ちなみに作品の最初の仮タイトルは「火星のプリンセス」だったんですよ。ストーリーは全然違うんですけど、エドガー・ライス・バローズの有名な古典SF小説に同じタイトルの作品があるんです。そういう点でも、SFでは王道の舞台だし、火星でいこうということになりました。
―今回はオリジナル作品ですが、原作のある作品との違いは感じますか?
原作がある場合は、それを踏まえてどう作るかという発
想になるんですよね。原作にゴール地点が書いてあるから、あとはそのゴールにどうたどり着くかを考えればいい。だけど今回はそのゴール地点をまず考えなければならなかったので、そこが一番大変でした。何度も話し合って、シナリオも何稿も重ねて、どれが自分たちの一番やりたい作品なのかを考えて。アニメーションは集団作業なので、みんなが合意しないと先に進めないところもあるんですよね。その合意する地点を決めるのに時間がかかりました。
―原作がないから、たとえば設定にあいまいな部分が発生したりはしませんか?
いえ、今回はロボットものということもあって、むしろ設定が膨大なんですよ。「ここはどうやって動いてるんだろう」みたいなことからロボットの弾丸のサイジングまで、いろいろ考えないといけない。最初は正直、「これは大変そうだな」と思いました(笑)。たとえオリジナル作品でも、学園ものや日常ものだったらそこまで大変じゃないと思うんですけどね。ロボットの身長も、何メートルが一番いいのか、たとえば18メートルだったら高すぎるのか低すぎるのかとか、一つ一つ検証しながらやりました。
―今回、監督としてどんなチャレンジのある作品になっていますか?
実はロボットものの監督をやるのは初めてなんです。だけど作り始めてわかったのは、自分がけっこうロボットものが好きだったんだということ(笑)。振り返ってみると僕が小学校・中学生くらいの頃はロボットアニメの全盛期で、ロボットものの一番いい時期に触れていたんです。小学校の頃からガンプラ世代でしたし、中学生になってからもサンライズの作品なんかをずっと見ていました。そこでいざ自分がロボットものをやるとなれば、ロボットものをちゃんと作るということ自体がチャレンジなんですよね。だから見せ方にしても、脚本のアイデアにしても「こういう形でロボットのかっこよさを出したい」と、いろいろと考えるところがありますね。今までありそうでなかったような描写を表現したいと狙っています。
―子供の頃に好きだったアニメを思い出しながら作る部分もありますか?
そうですね。「自分は子供の頃、なぜあの作品があんなに好きだったんだろう」と振り返ってみて、「ここがよかったんだな」というところがわかったら、今の技術だとどう作れるかを考えてみたり。
―今回のストーリーが少年少女がロボットに乗って戦争をするという、伝統的なリアルロボットの系譜を感じさせるものになったのも、ご自身が好きだった作品へのオマージュがあるのでしょうか?
それもあると思いますが、そもそもこの企画自体が「王道のロボットアニメをやろう」というものなんですよね。最初からそう言われたわけではないですけど、なんだかんだ言って王道ものって好きだよねというのが、打ち合わせするうちにわかってきた。だから監督としても、変化球じゃなくて、直球のストレートで重くて速い球を投げろって言われてるんだろうなと感じています。変にひねらなくていい、と。
―しかし「王道」というのも難しそうですよね。単にベタなことをやればいいというわけでもないでしょうし。
たしかに、今の時代は価値観がいろいろあるので、何をもって王道と呼ぶのかわからないとも言えますね。今でもロボットものの作品ってたくさん作られていますけど、その中でどれが王道らしいかと言われたら、わからないですし。
―あおきさんとしては、どんな作品が王道のロボットアニメと呼ばれると思いますか?
個人的には、ロボットが最後の2分くらいだけ出てくるのではなく、プロットの中心にいる物語だと思うんです。僕は作品を分析的に見ることはしないんですけど、改めて過去の名作と呼ばれているものを振り返ると、やはりそう思う。だから、ロボットを外すと成立しないストーリーって何だろうと考えながら作っています。ロボットを出さなくてもストーリーが成り立つような作品は作りたくないですね。ロボットものであることに殉じたい。自分が小学校や中学校の頃に毎週テレビにかじりついていたロボットものの感じ、ロボットのかっこよさとか、ワクワクする感じを出せたらいいなと思っています。そうやって、自分にとっての王道が作れたらいいなと思いますね。
―それが同時に、少年少女を中心とした戦争ものでもあるわけですね。
そうです。ロボットに乗り込む子供たち、主人公や敵の火星サイドのキャラクターたちを、ちゃんと感情移入してハラハラドキドキできるように描きたいと思っています。だから「ロボットものってあまり興味ないな」という人も、キャラクターをきっかけに物語に入っていけるようにしたいです。幅広い皆さんが楽しめる作品にしますので、ぜひご期待いただければと思います。
あおきえい
アニメーション監督、演出家。アニメーション制作会社AIC、フリーを経て、現在は自らが取締役を務める制作会社・TROYCA所属。主な監督作品に「劇場版 空の境界 第一章『俯瞰風景』」「劇場版 空の境界『 未来福音 extra chorus』」「喰霊-零-」「放浪息子」「Fate/Zero」などがある。
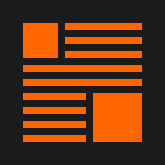
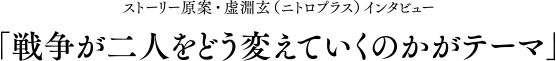
aaaaaaaaaaaa
最初は、まだアニメ『Fate/Zero』をやっていた頃だったと思います。アニプレックスの岩上さんから「次はロボットものをやりたい」と雑談レベルでお話があったんです。そこからあおきさんを監督に…など少しずつ具体的になっていき、定期的にブレストをして内容を考え始めました。いま調べてみたら、2012年の2月にプロットの草稿を作って、5月に第一稿を上げていたようです。でも、そこに至るまでにも紆余曲折あって、方向性に関してはかなり悩みに悩んだ記憶があります。
―どういう部分で悩んだのでしょうか?
最初から、とにかくロボットものをやろう、という話ではあったのですが、じゃあどういうロボットものにしようか、という部分でぐるぐるぐるぐる回っていたんです。「王道」という言葉を何度も言っていましたね。奇をてらわない王道。それをキーワードにしていました。ロボットものの原点回帰みたいな企画をやりたいねというのが根底にあったんです。しかし、じゃあ王道って何だろうという、その言葉の解釈について何度も話し合った覚えがあります。たとえば、あおきさんの切なる思いとして、メカには顔が付いていてほしい、とか(笑)。でもそれに対して「そもそもロボットに顔があるのってどうなの?」というようなことを延々と話したり。
―火星と地球の勢力に分かれて、主人公とライバルがいて、というような設定が生まれたのも、王道のロボットアニメについて考えた結果ですか?
そのあたりが、結果的に残った芯の部分だと思います。実は最初はもっと違う話だったんです。ゲームの「モンスターハンター」みたいなのをやろうよっていう案で。つまり、ものすごく巨大な敵ロボットを、小さなロボットたちがチームを組んで倒すというような極端なアイデアだった。でも、やはり王道っぽくないなということでやめたりして。そんなやりとりを経て、だんだん方向性が決まっていきました。
―では、王道と言われて、なぜ現在のような方向性になったと思いますか?
「王道」とあわせてもうひとつ、「大河もの」というキーワードがあったんですよ。つまり長いスパンの話で、大河ドラマのイメージで、という提案がされていました。それで視点を固定せずに、群像劇みたいな方向でやろう、ということになった。主人公サイドだけじゃなくて敵サイドも深く掘り下げていくべきだし、むしろ火星と地球、どっちが主人公サイドとかはっきり決めなくてもいいんじゃないか、という気持ちがありました。
―戦争の中で人間ドラマが描かれる、戦記ものみたいな感じですか?
そうですね。
―全く未知の異星人を敵にする案はなかったのでしょうか?
なかったです。最初からコンセプトに、人間と人間を戦わせるという案がありました。人間以外の者と戦っても、王道にならないので。そこは最初からブレませんでしたね。
―ではそこで、特に「火星」が舞台として選ばれたのは、なぜなのでしょう。
これも、王道のロボットものというのを考えた時に、やっぱり宇宙に行ったり地球に行ったり、いろんなフィールドの戦場を転々としていく感じがほしいよねということになったんです。宇宙でも戦わせたいけど、宇宙だけに限定したくないね、という。そこで、太陽系の中でもわりと地球と近さのある舞台ということで火星が選ばれたように思います。
―過去に王道と呼ばれたようなロボットアニメを意識することはありましたか?
昔の作品をそのまま作ってもしかたないですからね。むしろ「昔の作品はどこがよかったんだろう」「なぜ自分たちは、あれが好きだったんだろう」ということを、ずっと話していました。
―今回は、あおきさんが監督ということですが、最初にスタッフが決定した時はどんな作品になると期待しましたか?
『Fate/Zero』をはじめとする鉄壁の信頼感がありましたから、押さえるところを押さえた娯楽作でありつつ、ハードな手触りのある、いいものにしてくれるだろうと思いました。
―物語を考えるにあたって、「監督があおきさんだから、こうしよう」という部分もあったのでしょうか。
いいえ。むしろ、あおきさんの方から要望をがんがん出してくれたので、それに合わせて話を作っていくといった感じでした。
―あおきさんのこだわられたポイントというのは、どういう部分だったのでしょう。
物語の力点の置き方でしょうかね。世界観よりも主人公たちの視点や心情に沿って話を組み立てていくという点へのこだわりが大きかったと思います。特に第一話から第三話くらいまでは、物語の冒頭ですし、時間もかけました。最初、僕は大河ものとか戦記ものとか、その辺りのキーワードに引っ張られてしまう部分が多かったんですが、あおきさんの案でもっと人間関係のほうに寄せようということになって。その方針に合わせて、シナリオにどんな要素を入れて何を削るかという取捨選択をしていったところがあります。
―虚淵さんとしては、王道の作品を、自分なりのスタイルで変えようという気持ちはありましたか?
いえ、「王道」っていう言葉の重みがあるので、むしろ変えちゃいけない、奇をてらったことをしちゃいけないのかな、という気持ちがありました。今まで自分がやってきたスタイルをある意味では封印して、手堅い将棋ってどんなものだろうと考えながら作っていくような感じでしたね。「色物じゃないものって、どうやって作るんだろう」と。今まで色物ばっかり作ってきたから、難しかったですよ(笑)。
―では、そこで虚淵さんならではのカラーはどのように出ていると思いますか?
今回の自分の仕事はあくまで物語の基盤作りに徹してますので、実際に表面的なカラーとして出てくるのはその土台の上に他のクリエイターの方々が構築してくれた部分だと思います。それでも基盤は基盤でちゃんと遵守してもらってますから、それなりに匂い立つ雰囲気としては残ってるんじゃないかと。
―ということは、自分のカラーをあまり前に出さないというのも、今回の作品での挑戦ではあったのでしょうか。
王道というのも、なかなかやる機会があるものではないですからね。結果的にはいろんなスタッフと一緒に物語を作っていける作品になったので、そういう意味でのチャレンジは達成できたかなと思います。自分の個性だけで押していくようなワンマンなものにはなっていません。スタッフ内での共通見解を固めて、いろんな人に書いてもらえるものになった。それを目指した企画という意味では、うまくいったと思いますね。
―あおきさんからコンテが上がってきて、どう思われましたか?
けっこう手探りで初稿を書いた物語ではあるんです。それもあって、アニメにするのに時間と手間のかかる話だったと思うんですよ。だけどそれをきれいにまとめてくれて、さすが『Fate/Zero』をやってくれた人だなと思いました。そういう人だからこそ、自分が今回のような話をお届けできたという気もしますね。こちらが期待していた部分を、期待以上のものとして作っていただけて。もちろん脚本の段階で抱いていた不安もすべて解消されました。書きながら「これでいいのかな」と思っていたところが、コンテを見た瞬間「うん、やっぱりよかったんだ!」って思えるような、そんな安心感がありました。
―虚淵さんならではの物語性に期待する人もいると思うのですが、それは残っていると思いますか?
ええ。大筋の部分は何も変わってないですからね。二人の少年の関係性の物語であり、それが移り変わっていくのを描いていく。それが基本になっています。
―特に人間関係を大きなテーマにしているわけですか?
そうですね。その関係プラス戦争というか…戦争という状況が、二人の少年をどう変えていくのか、というのが大きなテーマだと思います。
―人間関係のバックグラウンドに戦争が強く影響しているわけですね。
そこはやっぱり「大河もの」というキーワードが関わってきていると思います。大河といえば戦記もので歴史もの、というイメージが強かったんじゃないですかね。
―「戦争によって少年たちが変わっていく」というと、ネガティブな意味も感じますね。
それは当然、あり得ると思います。戦争ですから。ひたすら人間賛歌で押せるものでもないので。圧倒的な環境の中で人間が揉まれてどうなるかといえば、いいほうにばかり転がっていくわけじゃないですし。
―深いテーマ性を感じさせますが、視聴者としてはどう見たらよいと思いますか?
僕としては、今回に関してはそんなに身構えないで見てもらった方がいいんじゃないかと思うんですよね。ただ視聴者をびっくりさせるより、堅実に内容を積み上げていく作品だと思っています。だからむしろ今まで虚淵玄が苦手だと思っている人にも見てほしいですね。「このくらい手堅い仕事もできますよ」というのを見てもらいたいと思います(笑)。
―しかし虚淵さんが過去に手がけた脚本だって、根底には骨太な物語の強さがありましたし、その意味では王道の物語でしたよね。
誰もが求めている部分ですからね。だからこそ大事にしなきゃいけない部分だと思います。過去に王道と呼ばれたロボットアニメだって、そのポイントを大切にした骨太な物語だったからこそ、今に生き残っているわけですからね。そういうテイストは継承したいというのは、僕だけでなくみんなが思っていたことです。しかしそれも、いろんな人の助けを借りながらやっとできたという感覚はあります。僕一人でやっていたら、少年二人の話として作り上げることはできなかったと思います。そういう意味でもチームで作っているからこその作品だと思いますので、構えないで見ていただければ。
虚淵玄
PCゲームメーカーニトロプラス所属のシナリオライター、小説家。主なアニメーション作品は「魔法少女まどか☆マギカ」(脚本)「Fate/Zero」(原作)など。「仮面ライダー鎧武」では初の実写作品の脚本を手がける。